「私が初めて社会における分断を意識したのは、1990年代の日本での一つの小さな出来事でした。電車の中で、ウォークマンのイヤホンからの音量について注意されたその瞬間、第三者である車掌がイヤホンで聞いている本人と乗車している周囲人を分けていることに違和感を覚えました。この課題は、ウオークマンの周囲の人たちが決めればいいと思ったからです。もう少し踏み込むと、周囲でそれができなければ、コミュニティーが維持できないということとも繋がっています。
それから30年後、日本に戻ってくると至る所に「分断」が見られます。求人広告に、年齢制限、男女制限、海外でコレをやったら即アウトです。そして、非正規雇用に対する処遇が、期間限定で正規雇用に行くのではなく、リセットされて再び非正規雇用になる仕組み。
米国では、非正規社員が正規社員と同じ仕事を半年以上した場合は正規社員にしなければならないという規則がありました。(少なくとも私の在米中は・・・。)
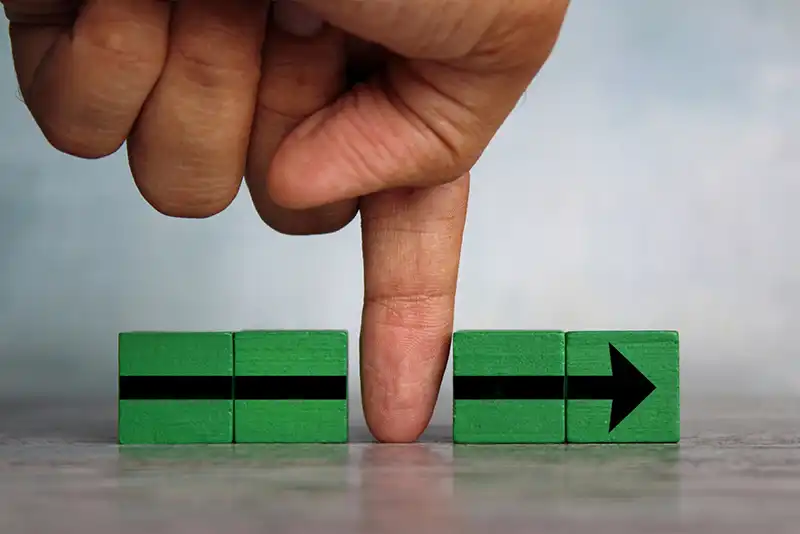
こうやって見て行くと、分断は日本の社会では広く浸透しており、分断された側は不利益な状態になる。これは、富の二極分化を生み出す分断ともつながっています。
非正規雇用という面で見ると、米国では、優れた能力を持ちながら組織の中では働きたくない人は契約社員という選択があります。その人の給与は、正社員よりも高いのが普通です。その理由は正社員には会社から福利厚生が与えられます。(健康保険とか、交通費補助とか、ランチ提供とか、場合によっては退職金とか)
それらが無い分給与が嵩上げされるのです。これは本人の選択であり経済的な不利益にはなっていません。
日本と米国の違いは働く人の権利意識?
労働側の権利意識の違いは大きいでしょう。そして経営側の「人材」に対する見方の違いがあると思います。
日本は新卒一括採用に見られるように、労働力の質をあまり問いません。しかし米国は、特定の技能を持つ社員を個別に採用します。
これは、個々の社員を見ているわけです。
だから、不景気になって退職者を出す場合、日本では一律に10%削減とかやります。その結果、他社でも使える優秀な人ほど逃げ出してしまう。またやめさせられた人は、解雇された人と見られます。
米国の経営者はもう少し巧妙で、レイオフする数ヶ月前に組織変更します。残したい人は別部門に移ってます。そして、既存の部門を閉鎖して、解雇するのです。辞めさせられた人は「所属部門が閉鎖になった」という理由でやめたので、傷つきません。

分断の話が、雇用、解雇の話になってしまいましたが、根底に横たわる意識は人をいかに(積極的に)働かせるかです。安くて身分が不安定では人は安心して(積極的に)働けません。
ここで、経営者の人材に対する見方を変えないと、会社にとっても雇用される人にとっても活力ある会社にはならないと思います。
働く側も、もっと権利意識とスキルの向上で、会社や組織に対して物申すになれないのではと心配しています。
みんなが一体となって成し遂げる仕組み、日本にとって今急いで作り上げなければと考えます。
結論
「分断の問題は、単なる雇用や解雇の話に留まらず、経営者と労働者双方の見方の変革を求めています。みなさんのコメントや意見を歓迎します。」
